明日の[ネット]広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法 [を忘れてしまった業界への一言]―ATS Tokyo 2024イベントレポート
by on 2025年5月01日 in ニュース
![明日の[ネット]広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法 [を忘れてしまった業界への一言]―ATS Tokyo 2024イベントレポート](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/05/takahiro-main.jpg)
デジタルメディアとマーケティング業界の有識者が一堂に会し、業界の最新動向についての議論を行うイベント「ATS Tokyo 2024」が2024年11月22日、都内にて開催された。
ATS Tokyo 2024のトリを飾るセッションには、2年連続で高広 伯彦氏(社会構想大学院大学 コミュニケーション・デザイン研究科 特任教授)が登壇。
「明日の[ネット]広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法 [を忘れてしまった業界への一言]」と題したタイトルで、プレゼンテーションを行った。プレゼンテーション後のモデレーターはExchangeWire JAPAN 編集長 野下 智之が務めた。
この特徴的なタイトルは、高広氏が電通に勤務していた時の上司、佐藤尚之氏が執筆した「明日の広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法」(2008年/アスキー)をアレンジしたもの。なお、タイトルの利用については、佐藤氏に許可を得たうえでのことだそうだ。
本セッションでは、長年業界を見続けてきた同氏が、消費者にとって悪しきものになりつつあるインターネット広告の現状を、どうすれば良い方向へ導けるのか、という議題が改めて提起された。
20年以上にわたり広告、マーケティング、デジタル領域の企画開発・事業開発に携わってきた高広氏は、いくつかのキーワードを軸に、インターネット広告の歴史を振り返りながら、インターネット広告業界が抱える課題を紐解いた。
クッキーレス問題、ユーザビリティを犠牲にした過剰な広告表示、不快なクリエイティブ、不公平なアプリ広告の計測環境など、デジタル業界の課題は山積みだ。高広氏は、パブリッシャー側の問題、広告主側の問題、技術的な問題、エコシステムの問題の中で、現在最も深刻な問題はエコシステムの問題だと指摘。この問題の解決には、パブリッシャーや広告主だけでなく、業界全体での協力が不可欠だと述べた。そして、こうした問題の根本原因として、広告の歴史の軽視、過去の失敗からの学びの欠如を挙げた。
高広氏は、20年間アドテク業界を見てきた中で、まるでデジャヴのように、業界が同じ失敗をしているところを4~5回は見てきたという。
「過去の同様の失敗を、業界は忘れてしまっている。あるいは、現在の業界関係者は、過去にそのような問題があったことすら知らないのではないか」
と述べ、一度立ち止まり、歴史を振り返って考えることの重要性を訴えた。
また、重要でありながら忘れられている概念として「パーミッションマーケティング」を挙げた。「インタラプションマーケティング」(日本では「土足マーケティング」と訳された)の対義語として登場したパーミッションマーケティングは、顧客の許諾(パーミッション)を得て情報を提供するという考え方だ。当時主流だったメールマーケティングを基に生まれたこの考え方は、顧客ニーズを把握し、適切な情報を提供するというもので、現在のインバウンドマーケティングやインテントセールスなど、あらゆるマーケティング・セールス領域の核となる重要な概念と言える。しかし、業界はこの基本的な考え方を忘れ、新しいマーケティング手法にばかり目を向けていると指摘した。
さらに、クッキーとユーザー体験を阻害する広告についても言及。
「クッキーは本来、ユーザーが毎回ログインする手間を省くために用いられていた。しかし、今は違う。ユーザーのための技術だったことを忘れている。『誰のためのテクノロジーなのか?』という視点が業界に欠けている」
と指摘した。続けて
「インターネットが定額制ではなく、ダイアルアップ接続だった時代、ユーザーは接続時間に応じて料金を支払っていた。つまり、ユーザーは広告を見るためにお金を払っていたと言える。この時代に生まれた『広告は情報として有益でなければならない』という価値観は、インターネット黎明期に、メディア体験を阻害する広告を排除する動きにつながった。邪魔な広告を排除するという考え方は、20年以上前から存在していたにもかかわらず、再び邪魔な広告が問題となっている。これは、業界が過去の教訓を忘れてしまったからだ」
と述べた。
今広告業界に必要なのは
イノベーションではなくリノベーション
高広氏はGoogle時代に、Google Print AdsやGoogle TV Ads(後にGoogle TVと改称)の開発に携わっていた。
Google Print Adsには、広告主のリクエストをパブリッシャーが価格の安さを理由に拒否できる「リジェクトオーバーカウンター」という仕組みがあった。これは単なる拒否機能ではなく、拒否回数の上限を設定することで、広告主とパブリッシャーの間の価格交渉を促す双方向のネゴシエーションを実現するためのものだった。
また、GoogleのテレビCM販売プラットフォーム「Google TV Ads」の開発にも携わっていた。Googleの検索連動型広告のような革新的な広告とは異なり、Google TV Adsは従来の広告ビジネスの仕組みを改善する、いわば「リノベーション」を目指していた。Googleアナリティクスとの連携によるテレビCM放映時のトラフィック増加などのデータ分析機能に加え、CM制作会社と広告主の連携機能、広告テキストからの自動広告生成機能なども開発していた。
高広氏によると、これらの取り組みの背景には、ジョン・ワナメーカーの有名な言葉「広告費の半分は無駄になっているが、どの半分かはわからない」に対するGoogleの危機感があったという。
「この状況を打破するために、Googleはシンプルな広告プラットフォーム構想を立ち上げ、全国規模のビジネス展開を目指していたが、構想の中心メンバーが離脱したことで頓挫してしまった」
と明かした。
崩壊したビジネスモデルに必要なのはイノベーションではなくリノベーションだ。
そして、現在の広告業界に必要なのもイノベーションではなくリノベーションだと、高広氏は考察する。
「現在のアドテク業界には、革新的な技術開発(イノベーション)よりも、既存システムの改善・改良(リノベーション)が必要だ。近江商人の「三方良し」の精神のように、広告業界では、ユーザー、パブリッシャー、広告主という三者の利益のバランスがとれたエコシステムが構築されることが理想であり、アドテク事業者は、この三者の均衡を保つ役割を担うべき存在である。だが、現状は特定のプレイヤーに偏っているアドテク事業者が多い。これが現在の広告業界に様々な問題が生じている理由のように思える。
この問題を解決するために、1つの事例を紹介する。昔、検索窓にキーワードを入力すると、30日以内に検索結果を郵送するというGoogleのパロディサービスを行った人がいた。このサービスは一見時代遅れのようだが、Google の本質的な機能、つまり「情報を提供する」というミッションを捉えていると言える。
この事例から学べることは、技術の進化に囚われず、自らのミッションの本質を見極めることの重要性だ。たとえ古い技術を用いたとしても、本質を捉えていれば価値を提供できるはずだ」
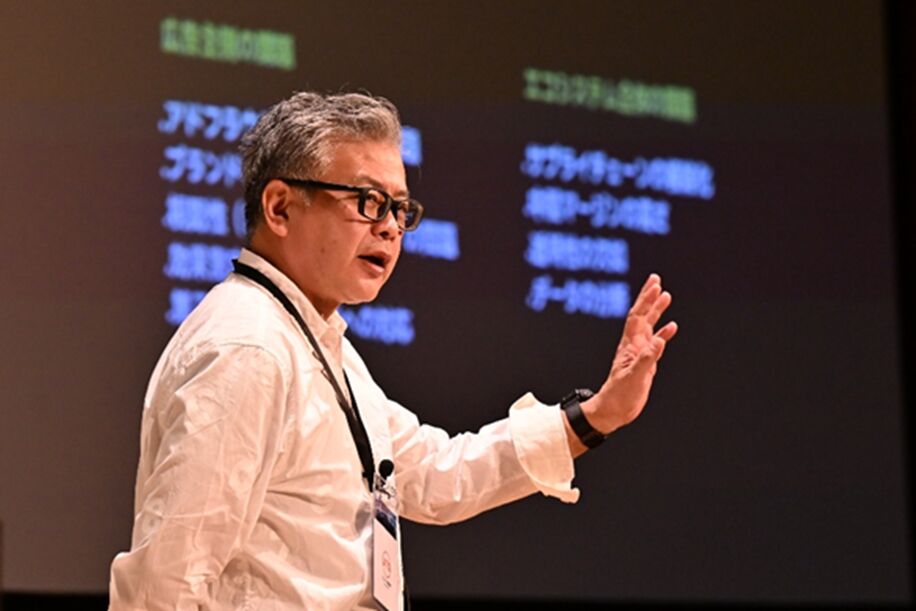
もっと面白い広告を作るべし!
セッションの最後には高広氏と野下のQ&Aが行われた。
まず野下から「邪魔な広告の既視感」について聞かれると高広氏は
「今、ユーザー体験を阻害する広告と言えば動画の合間に出てくる広告やポップアップ広告ではないでしょうか? 昔もJavaScriptをオンにしておくと画面いっぱいの広告が出ました。当時はあまりにもそのような広告が出すぎて、ワームやトロイの木馬のように、広告がマルウェアみたいに扱われてしまった時代がありました。今、またその歴史を繰り返しているのではないだろうか」
続いて「ユーザーにとって有益な広告とは?」という質問に対しては
ユーザーにとって興味、関心があるタイミングで表示される広告、そしてユーザーが見たくなる広告を挙げた。
「広告が邪魔になる理由を端的に言えば“面白くないから”。YouTubeやTikTokで流れる広告をユーザーが邪魔に感じる理由は、観ているものより広告の方が面白くないに尽きるでしょう。ただ、昔もテレビでCMが流れている時間は“トイレタイム”と言われていて、ユーザーにとっては嫌われていた。だからこそ、CMクリエイターたちは観てもらえるように、面白いCMを作る努力をしていた。ところが今はどうか。みなターゲティングでリーチすることばかり考えていて、広告のクリエイティブを軽視している。面白い広告ならば、アテンションも必然的に上がる。それが広告の本質だと思う」
と述べた。
最後に「先ほど高広氏がおっしゃったアテンションと、今新しく出てきた指標であるアテンションは、相互作用するものなのでしょうか?」という質問には
「“アテンション”という言葉には、一般的な意味や心理学的な意味、そしてデジタル広告業界で使われる意味と、様々な解釈が存在する。デジタル広告業界で使われるアテンションにおいてはまず、定義を整理する必要があるだろう。広告業界でアテンションを扱う際、アテンションをどのように定義するかは、効果測定の観点から共通認識を持つべき重要な課題だ。
しかし、心理学や一般的な意味でのアテンションについても今一度考える必要がある。
一般的にアテンションとは“注目される”ことであり、注目されるためにはどうすれば良いかを考える必要がある。つまり、アテンションを上げるためには、注目を集めるための施策が不可欠だ。
心理学には“選択的注意セレクティブアテンション(選択的注意)”という言葉がある。これは、カクテルパーティーのように騒がしい環境でも、自分に関係のある会話は自然と耳に入ってくる現象で『カクテルパーティー効果』とも呼ばれる。
効果的な広告を作るためには、このセレクティブアテンションを誘発するようなクリエイティブや広告の出し方を考える必要がある。つまり、広告指標としてのアテンションと、人間の心理学的側面から見たアテンションは分けて考えるべきだ。そうすることで、より効果的な広告を展開することが可能になるだろう」
と締めくくった。

ABOUT 町田貢輝
ExchangeWireJAPAN 編集担当 日本大学法学部法律学科卒業。編集プロダクション、出版社でエンタメ、健康、IT関連の雑誌と書籍の編集・進行管理に従事。2024年に調査・コンサルティング会社シード・プランニングに入社。DX領域のメディア運営全般ならびに、調査研究を担当する。




