「質」を問い直す広告投資-“終焉”か“復活”かを決めるのは誰か-ATS Tokyo 2025 セッションレポート
by on 2026年1月21日 in ニュース

「メディアの終焉」か「復活」か〜広告主の投資先はどこに向かうのか〜」と題した本セッションには、パーソルテンプスタッフ株式会社 執行役員CMO 友澤 大輔氏、 小林製薬株式会社 新規事業準備室 兼 広告販促部 戦略スタッフ 大槻 開氏が登壇し、ExchangeWire JAPAN 編集記者 町田 貢輝がモデレーターを務めた。
広告主サイドの現場感を起点に、コスト効率指標偏重がもたらしたメディアエコシステムの歪み、リーチの「質」をどう測るか、そして広告主が求めるパートナーシップのあり方まで、両氏は自身の経験を交えながら議論を展開した。ウォールドガーデンへの投資集中は意図ではなく構造的必然であるとし、そのうえで“次の選択”をどう拓くか-広告主が直面するリアルが語られた。
セッション登壇者
- パーソルテンプスタッフ株式会社/執行役員CMO/友澤 大輔 氏
- 小林製薬株式会社/新規事業準備室 兼 広告販促部 戦略スタッフ/大槻 開 氏
- ExchangeWire JAPAN/編集記者/町田 貢輝(モデレーター)
リーチの「量」と「質」が乖離する現場-広告主が抱える根本的課題
本セッションの冒頭、両氏は広告投資の現状を語るにあたり、まず「リーチ」概念の揺らぎに触れた。大槻氏は、P&G 在籍時の経験として、同社が長年「REE(Reach Effectiveness Efficiency※1)」を中核に置く独自の合理的メディア運用を徹底してきた点を紹介した。特に「コスト・パー・リーチ」を最適化する文化は強固で、テレビや TVer など確実性の高い手法が選択されやすい構造にあると説明する。
一方、同じ P&G 内でも一部ブランドでは“Not all reaches are equal”の考えを掲げ、「効果」を独自指標として設定していたという。ターゲットの文脈や意図、ストーリーテリングまで含めて価値を定義し直すアプローチであり、「リーチは量だけでは語れない」という視点も存在していた。
しかし、日用品や化粧品メーカーでは、多様な商品群を抱えるため、社内説明の難易度は高く、「ブランドにとって本当に価値のあるリーチとは何か」を噛み砕いて共有することが容易ではないと語る。結果として、効率性の高い手法へ投資が集中するが、それが最適とは限らないという葛藤を抱えている。

友澤氏も同調し、広告主の視点から「CPAやROIを追いすぎた結果、広告品質が毀損し、メディアのエコシステム自体を弱らせた可能性がある」と指摘した。「可視化できるから割り算して安くする」という文化が強まりすぎたことが、リターゲティングの濫用や、メディア面の価値下落につながったという実感を示した。
また、AI生成コンテンツの急増やタッチポイントの細分化によって、従来以上にリーチ最大化と成果最大化を同時に追う難易度が高まっていると述べ、「量」と「質」を両立するメディアプランニングの複雑化を現場の課題として整理した。
※1 REE(Reach Effectiveness Efficiency)
Reach(リーチ):「どれだけ多くの異なる人々に情報が届いたか」を示す指標。
Effectiveness(エフェクティブネス):「設定した目標に対して、どれだけ効果があったか」を測る指標。
Efficiency(エフィシエンシー):「投入したコストやリソースに対して、どれだけ無駄なく成果を上げられたか」を測る指標。
ウォールドガーデン偏重は“意図”ではなく“構造”-広告主を縛る条件とは何か
議論は次第に「なぜウォールドガーデンが選ばれ続けるのか」という核心へ移った。
大槻氏はまず、「ウォールドガーデンへの偏りは“意図”ではなく“組織構造上の現実”」と強調する。新しい媒体や手法を試す際、企業内での説明負荷が大きく、成功事例の有無が判断に大きく影響するという。中間管理職を含む社内関係者の合意形成には「コスト・パー・リーチ」のような明快な指標が求められ、未知のメディアに投資するには説得材料が不足しがちである。
さらに、ウォールドガーデン自体も進化を続けており、AIを活用した運用機能拡張が加速する中、日々アップデートされる仕様へのキャッチアップだけで担当者は手一杯になってしまうと語った。視野が狭くなる構造的リスクを認識しつつも、「実務の観点で最も手堅い選択肢として残り続ける」という現場の実情がある。
友澤氏もこれに呼応し、「限られたリソースで効果を最大化するため結果的にウォールドガーデン中心になる」と述べた。検索・バナー広告・SNSなど、少人数のチームでも扱いやすく、運用最適化が効く手法が優先されるためである。特にP-MAX(パフォーマンス マックス)※2のような統合型プロダクトは、短期的成果を確保する上で不可欠になっている。
一方で、友澤氏は「現在はCPCが高騰し、同じ市場に広告主が集中するほど単価が上昇する構造が加速している」と指摘。新規顧客獲得の限界が露呈しており、「ファーストペンギンとして新しいメディアを開拓しない限り、長期的なリーチ確保は難しくなる」との危機感を共有した。

また、大槻氏はブランド文脈に応じメディアが広がる例として、ヘアケアブランドの社会事化をテーマにしたキャンペーンについて触れた。新聞・ニュース媒体・SNS など複数 のメディアを連動させることで、ブランドの社会的意義を適切に届ける必要があり、 「理解あるパートナーによってメディア選定は大きく変わる」と述べ、ブランドのビジョン 理解が投資配分に大きな影響を与えるという点が示された。
※2 P-MAX(パフォーマンス マックス): Google広告のキャンペーンタイプ。検索、YouTube、ディスプレイ、Discover、Gmail、マップなど、Googleのすべての広告枠を1つのキャンペーンとして利用できる。
広告主が求めるのは“人”の理解と継続関係-パートナーシップの質が投資先を決める
議論の後半では、広告主がメディア・代理店・ベンダーに求める姿勢に焦点が当てられた。
友澤氏は冒頭から一貫して「パートナー選びは“人”で決まる」と強調する。AIが資料作成を担う時代、価値があるのは「どれだけ広告主の課題を理解し、熱量を持って伴走するか」という姿勢だと語った。
特に、新しいサービスを導入する際には「事例」が不可欠であり、数値だけでなく背景やプロセスまで含めた具体性が求められる。そのうえで、広告主が得たい情報はポジショントークではなく“第三者的にフラットに語られる成果”であり、そこには信頼関係が前提として存在するとの認識を示した。
一方、大槻氏は自身の経験として、広告主の内部事情を理解し共に乗り越える姿勢の重要性を語った。例えば、ブランドマネジメント、新規事業や AI 推進のようなテーマでは、上層部が突然 のアイデアを提示し、担当者が即座に具体化を求められる場面が多いという。こうした場面でともに考え、社内説得の材料を提供してくれるパートナーほど、信頼を寄せられると述べた。
さらに、大槻氏は「Give & Take」を適切に成立させる関係性を重視するとし、支援側が熱意を持って提案し、広告主がそれに応えるという循環が必要だと語った。過去の経験として、データ購入やレポート作成など、明確な利益に直結しない行動が信頼構築に寄与した例も紹介し、パートナーシップは長期的視点で築かれるものだと強調した。
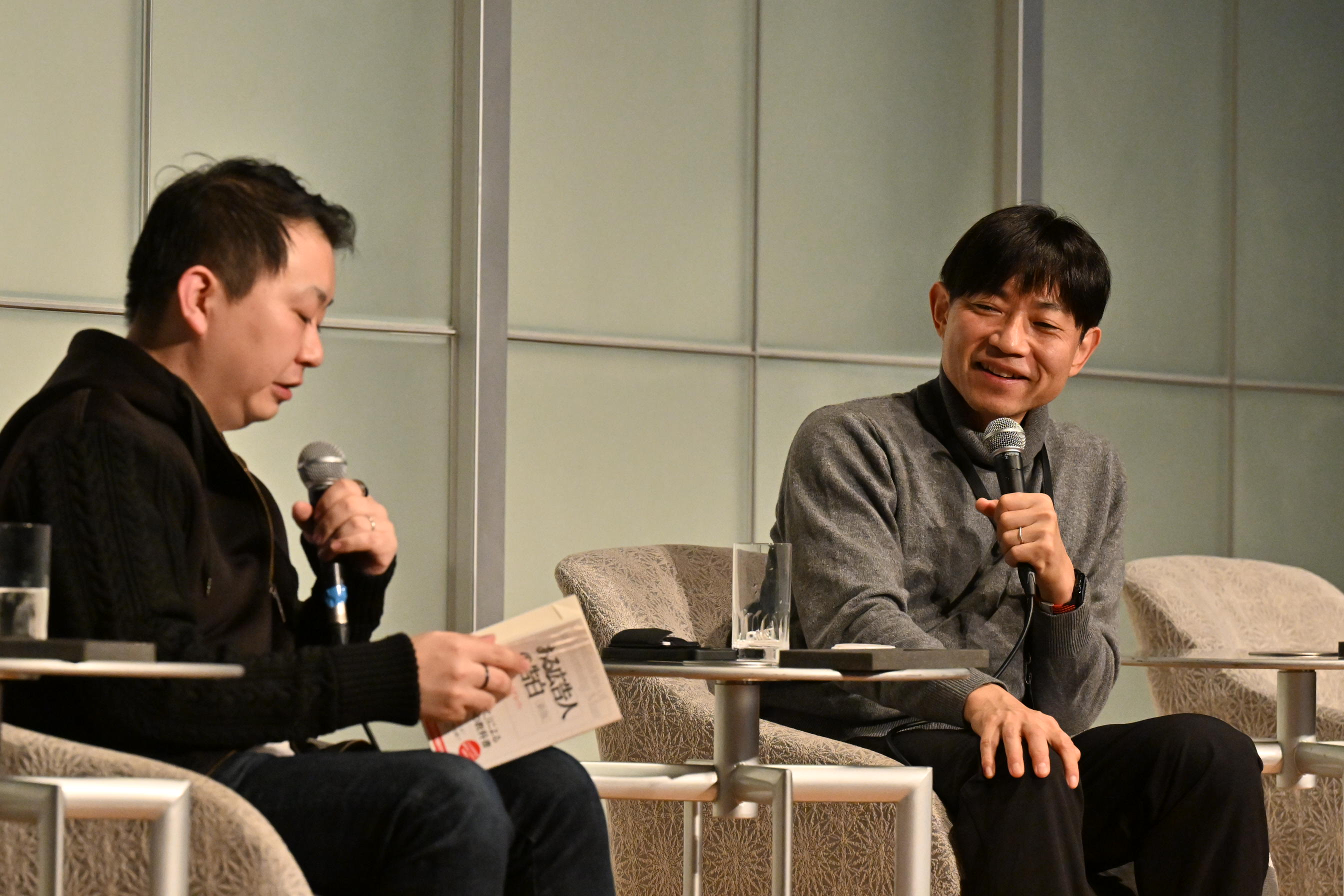
両氏はまた、提案が実際の投資に至るかどうかは「タイミング」に大きく依存すると指摘する。広告主が抱える課題と、パートナーが提供する価値が一致した瞬間に意思決定は加速するため、日頃からのコミュニケーションが極めて重要だという。ワンショットのアプローチではなく、継続的関係構築こそが成果につながるという認識が共有された。
最後に、両氏は「明日からできる一歩」としてそれぞれの視点を提示した。
大槻氏は、デイビッド・オグルヴィ著『ある広告人の告白』を紹介。クライアントとの関係構築に関する普遍的な知見を得られる名著である本著の熟読を最初の一歩として呼び掛けた。
友澤氏は「AI時代だからこそ“人を見る”」姿勢を改めて強調し、一度断られても諦めずに対話を続けることが新しい挑戦につながると締めくくった。

ABOUT 町田貢輝
ExchangeWireJAPAN 編集担当 日本大学法学部法律学科卒業。編集プロダクション、出版社でエンタメ、健康、IT関連の雑誌と書籍の編集・進行管理に従事。2024年に調査・コンサルティング会社シード・プランニングに入社。DX領域のメディア運営全般ならびに、調査研究を担当する。





