YouTubeに出稿する全ての広告主へ-ZEFRが目指す、動画広告運用の価値向上[インタビュー]
![YouTubeに出稿する全ての広告主へ-ZEFRが目指す、動画広告運用の価値向上[インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2021/06/zefr-2-525x350.jpg)
成長を続ける動画広告市場において、王道を行くのは紛れもなくYouTubeであることは疑いの余地はない。動画広告を出稿するほぼ全ての広告主が出稿するYouTube上で、クリエイティブ以外の領域で、広告運用の差別化を行うのはなかなか容易ではない。
三井物産とLegolissが日本に持ち込んだZEFRというサービスは、広告主や広告代理店の動画広告運用の現場を大きく変える素地を持っているようだ。
このプロダクトを日本で展開することになった背景やその特徴、広告主や広告代理店にとってのメリットなどについて、三井物産株式会社 ICT事業本部 デジタルマーケティング事業部チームリーダー 杉山悠介氏、株式会社Legoliss取締役 中嶋 賢氏(以下ケニー氏)、同プロダクトソリューション事業部 アカウントマネージャー 吉田 三璃氏(以下ミリ氏)、同 小西未紗氏(以下ミサ氏)にお話を伺った。
(聞き手:ExchangeWireJAPAN 野下 智之)
(Sponsored By Legoliss)
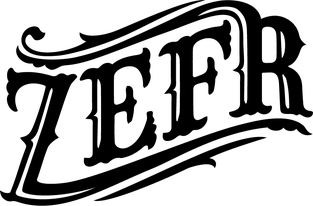
-自己紹介をお願いします
杉山氏:三井物産ではICT事業本部デジタルマーケティング事業部に所属しています。主に広告・マーケティング・CRMの領域で海外の先進的なテクノロジーやソリューションを日本で展開する役割を担って、これに伴うパートナー企業への出資業務なども合わせて担当しております。
新卒で博報堂に入社し、10年半ほどを過ごしました。この間は営業に8年、新規事業開発に2年を費やし、デジタルには深く関わってまいりましたが、2019年に三井物産に入社しました。
ケニー氏:大学卒業後に米国留学し、帰国後にはまず鉄鋼企業に入社しました。その後に現在のユナイテッド、当時のインタースパイアに参画し、モバイル広告業界で長年ビジネスを経験してきました。
次にキャリアの場を移したのは、2012年。この頃モバイル広告の需要はガラケーからスマートフォンへと移行する時期で、私自身も次のキャリアを模索し始めました。まさにアドテクの隆盛期で、日本ではフリークアウトが初めてRTBによる広告取引を始めました。ご縁あって友人からの紹介を受け、同社に参画することにしました。その後、フリークアウトの上場直前に人材企業大手が新規事業として立ち上げたアドテク企業のマーベリックへ参画し、5年強のキャリアを経て2019年7月にLegolissへ参画しました。
ミリ氏:私は、大学での米国留学時に現地のキャリアフォーラムで知った国内大手DSPに新卒で入社しました。広告運用と営業を4年弱経験したのち、2019年に三井物産に転職し、Legolissに転籍して現在に至ります。現在Legolisを通して三井物産が海外からソーシングしてきたプロダクト全ての営業、また運用まで総合的に担当しています。
ミサ氏:私は今年の4月に新卒でLegolissに入社し、現在は営業を担当しています。
日本の動画マーケティングで、いまZEFRが必要な背景
-三井物産とLegolissとの関係性について改めてお聞かせください
杉山氏:三井物産は2019年にLegolissを子会社化しました。これまで三井物産はデジタルマーケティングの領域では20年ほどビジネスを行ってまいりましたが、2019年頃からデータを使ったマーケティングで企業を支援していくビジネスに注力をしており、その中核となる会社としてLegolissを位置づけております。
-ZEFRをこのタイミングで日本に持ち込まれた背景についてお聞かせください。
 杉山氏:三井物産はデジタルマーケティング領域で事業を進めていく中で、ここ数年は海外から先進的なデータ関連のソリューションやテクノロジーを持ってくるビジネスを進めています。これまでもクロスデバイスのTAPAD、ジオターゲティングのFactual(現:Foursquare)などの日本展開を支援していましたが、これらに続く新しいソリューションを探していました。
杉山氏:三井物産はデジタルマーケティング領域で事業を進めていく中で、ここ数年は海外から先進的なデータ関連のソリューションやテクノロジーを持ってくるビジネスを進めています。これまでもクロスデバイスのTAPAD、ジオターゲティングのFactual(現:Foursquare)などの日本展開を支援していましたが、これらに続く新しいソリューションを探していました。
近年成長著しい動画広告市場を見ていて、この市場成長を取り込むビジネスに取り組むことができないか、そして昨今のプライバシーにかかわる個人データの利用規制をビジネスチャンスに変えられないかという二つの軸から、新しいソリューションを探しておりましたが、ZEFRはこの二つの条件を満たしておりました。
ZEFRは、世界でも限られたYouTube、Facebookそれぞれの公認パートナーでもあり、今動画広告が最も出稿されている2大媒体において活用することが可能です。
そして、コンテンツ単位でのターゲティングが可能なため、個人データを一切利用することなく運用することが出来るということに大きな魅力を感じました。
-ほかにも日本に持ってくる候補となるようなソリューションを合わせて検討していたのでしょうか?
杉山氏:はい。候補となる他のソリューションも数十社リストアップをして比較しましたが、その中でも技術的な優位性や、YouTube、Facebook双方とのパートナーシップを持っていることなどから、ZEFRに決めました。
-ZEFRを知ってから提携に至るまではどのくらいの期間を要しましたか?
杉山氏:約1年を要しました。昨年3月に私たちのほうからZEFRにアプローチをかけて、日本への進出の提案をしました。その後ずっとパートナーシップの協議を進めてきましたが、その過程でLegolissと一緒にZEFRのソリューションを日本の広告主の方にも試験的にお使いいただくというような取り組みも行いました。約20案件のトライアルを重ねて、成果が出ることを確認できたため、正式に資本業務提携をして日本に持ち込みました。
YouTubeでコンテキストターゲティング配信を実現
-ZEFRというソリューションについて、詳しくお聞かせください。どのようなソリューションなのでしょうか?
 ケニー氏:ZEFRは、クッキーに依存せずに、YouTube向け動画広告の配信面をコントロールすることが可能なプラットフォームです。日本においては現在YouTube向けのみですが、グローバルではFacebook向けの配信にも対応しており、将来的には日本でも利用できるようになる予定です。
ケニー氏:ZEFRは、クッキーに依存せずに、YouTube向け動画広告の配信面をコントロールすることが可能なプラットフォームです。日本においては現在YouTube向けのみですが、グローバルではFacebook向けの配信にも対応しており、将来的には日本でも利用できるようになる予定です。
先ほどの話の通り、YouTube側からデータを公式に提供してもらえることにより、大規模に、かつ高い精度で配信先をコントロールすることが可能となります。YouTubeが持つ膨大な広告在庫の中から、広告主様の求めるブランドイメージに沿う形で、量と精度の両方を担保したターゲティングコントロールが可能です。
広告主様や広告代理店様にとって、YouTube動画広告の運用においてクリエイティブ以外で競合他社と差別化をしてパフォーマンスを高めていくという手段は、これまで限られておりました。ZEFRは、YouTubeが伸び続けていく中で、動画を活用した取り組みをするためのソリューションに対するニーズがますます高まりつつあり、これに対応することが出来るプロダクトです。
杉山氏:ローカライズのところは、当初少し時間を要しました。配信のコントロールを米国側で行っていることから、私たちのほうでも最初はどのような面に配信されるのかというところは気にしており、ZEFR側から配信先のURLを全て出してもらって目視で確認を行いました。当初は日本語動画の解析の精度が欠ける部分もありましたが、徐々に機械学習で精度を高め、ZEFR側でも日本人の社員を採用するなどの対応を行いました。これにより、日本語の動画を解析するための精度は、改善をしてまいりました。
AIの技術が進む今でも、動画の中身を解析するということは、技術的にとても難しいことです。ですので、ZEFRは一部の動画に関しては人間の目で確認をして正解データを貯めて予測の精度を高めていくというアプローチをとっています。このようなやり方は「Human In the Roop」と呼ばれており、機械学習の工程に人が介在するという意味です。これが機械学習に依る精度を高めていくうえで、非常に有効なアプローチであるといわれています。
ZEFRで実現する、YouTube動画広告運用の価値向上
-ユニークポイントについて、お聞かせください。実際に競合となるのは、他のコンテキストターゲティング広告ソリューションでしょうか?
ケニー氏:コンテキストターゲティング広告を提供することが出来るプレイヤーは他にもいますが、そのほとんどはオープンWeb領域の配信面を対象としています。
ZEFRはコンテキストターゲティング広告を提供するプレイヤーであるものの、YouTubeに特化しており、YouTube公認のプレイヤーという強みがあります。
公認パートナーは、YouTubeの大規模なデータにアクセスすることが出来ます。YouTubeには常に膨大な動画がアップされますが、そのフレッシュな動画を解析し、管理画面へ動的に設定し配信することが出来るのは、公認パートナーであるZEFRだからこそです。
また、繰り返しになりますが、ZEFRは人の判断によって強化された独自のAI技術があり、動画に対して正確な解析をすることができます。コンテキストターゲティングは、これまでオープンWeb上のテキストやキーワードなどを対象に解析していました。Zefrは、動画広告に特化した、独自のソリューションを提供しているんです。
-セールス先はどのようなところがメインとなるのでしょうか?
ミリ氏:ZEFRに限らないことではありますが、グローバルのプロダクトとなりますので、外資系の広告代理店様への提案をすることも多いですし、またやはり大手総合広告代理店様も多いです。リリース後、ありがたい事に様々な代理店様からのお問合せが途絶えませんので、ニーズの高さを実感しています。
-実際の広告運用はどのように行うのでしょうか?どのようなチャネルで広告主に提供されるのでしょうか?
ケニー氏:広告主様や広告代理店様はAPIを通してシームレスに設定が可能です。既に運用されている既存アカウントの設定を何ら変更することがなく、追加的に配信先をコントロールすることが可能です。ですので、これまで運用担当者の方が独自に行ってきた工夫を活かしたまま、バージョンアップをすることが出来るのです。
導入時には、該当の広告商材と相性が良く、より効果が見込めそうなプレースメントのカテゴリを設定します。プレースメントのカテゴリは、現在80種類程度に分かれており、随時ZEFR側で増やしている段階です。
その後運用現場において、運用担当者がする作業は、ZEFR側から管理画面に届くリクエストを承認するだけです。配信の設定は全て米国側でツールを用いて行ないます。ZEFR側では人の目で強化されたAIで随時チェックが成されてクラスター分けをしています。
ミリ氏:広告主様から当社にお申し込みをいただいた場合、当社側でYouTube広告の運用まで実施することも可能ですし、いつもお取引をされている広告代理店様をつないでいただき、当社側でZEFRに関わる設定のみ実施することも可能です。
広告代理店様が持たれているアカウントのIDをいただければ、後はZEFR側と自動連係をすることが出来ますので、その後すぐに最適な広告運用が開始されます。
ミサ氏:グローバルでは誰もが知る世界的ブランドの広告主様にもZEFRを全面的にご活用いただいています。広告効果がとてもよいとの評価をいただいており、YouTube広告出稿の際には、必ずZEFRをご利用いただいております。
ブランドセーフティーとブランドスータビリティーを実現
-広告主は、実際にどのようなメリットを得られるのでしょうか?高い広告効果が得られる仕組みについて、解説をお願いします。
ミリ氏:ZEFRを使っていただくというメリットには、ブランドセーフティーとブランドスータビリティーの二つを実現できることが挙げられます。ZEFRでは、広告配信を行う際に、広告主様のブランドに毀損しないような配信面を、動画の中身を高い精度で判定して確保しています。そのうえで、ブランドスータビリティー、いわゆるブランド適合性の観点で、モーメントをとらえた広告配信をすることが可能です。ユーザーが見ている面やコンテンツの文脈にふさわしいタイミングで広告を出すことで、ユーザーにブランドメッセージがスムーズに受け入れられやすくなります。
 ミサ氏:これを実現するにあたり、繰り返しになりますが、ZEFRはYouTubeの公認パートナーであることから、YouTube上にアップされている動画に大規模にアクセスすることが出来る権利を持っています。その中から該当するブランドが広告を配信するにふさわしい面のみを抽出し、ZEFR側がブランドにとってのプレミアムな広告在庫をリスト化します。
ミサ氏:これを実現するにあたり、繰り返しになりますが、ZEFRはYouTubeの公認パートナーであることから、YouTube上にアップされている動画に大規模にアクセスすることが出来る権利を持っています。その中から該当するブランドが広告を配信するにふさわしい面のみを抽出し、ZEFR側がブランドにとってのプレミアムな広告在庫をリスト化します。
これを判別する上では、動画のタイトルや尺、Like数、Dislike数、説明文など、その動画に関する細かい項目までを読み込んだうえで、動画コンテンツの選別を行います。
人の目で強化したAIで判断するところは、特許も取得しています。配信先の選別においては、URL単位でホワイトリスト化をすることが出来るようになっています。従って、効果の高い広告運用が実現できるのです。
ケニー氏:広告代理店様の運用の現場では、これまでは配信面のコントロールを、手動で行っていたと伺っております。これをZEFRでは事前に自動的に行うことが可能になります。したがって、広告代理店様は、ZEFRを使うことでYouTube広告配信におけるアドベリフィケーション対策も行うことができるということにもなります。
-今後「ZEFR」をどのように普及させていきたいと考えていますか?
 ミリ氏:究極的には、YouTubeで動画広告を出稿している全てのお客様にお使いいただきたいと考えています。
ミリ氏:究極的には、YouTubeで動画広告を出稿している全てのお客様にお使いいただきたいと考えています。
広告主様は、ブランドセーフティーを担保しつつ、ブランドスータビリティーを追求して広告効果を高めるために、YouTube動画広告の配信先をしっかりと把握していくことが今後求められるようになります。そのため、ZEFRのようなソリューションは今後ますます求められるようになり、私たちは広告主様のYouTubeを中心とする今後の動画広告活用におけるサポートを、しっかりと行ってまいります。
ABOUT 野下 智之
ExchangeWire Japan 編集長
慶応義塾大学経済学部卒。
外資系消費財メーカーを経て、2006年に調査・コンサルティング会社シード・プランニングに入社。
国内外のインターネット広告業界をはじめとするデジタル領域の市場・サービスの調査研究を担当し、関連する調査レポートを多数企画・発刊。
2016年4月にデジタル領域を対象とする市場・サービス評価をおこなう調査会社 株式会社デジタルインファクトを設立。
2021年1月に、行政DXをテーマにしたWeb情報媒体「デジタル行政」の立ち上げをリード。




