iOS上のターゲティングと未来型コマースで差別化-InMobi独自の戦略とは[インタビュー]
幾多の事業者がひしめくオープンインターネット上の広告配信には、他社とは一線を画す尖った技術を持つことが求められる。AdAttributionKitという正規の手法をフル活用することでiOSユーザーへのターゲティング可能なDSPに加えて未来型コマースという、まさに尖った、しかも二つの全く異なるプラットフォームを有するのがInMobi社だ。来日した同社の最高ビジネス責任者に話を聞いた。 (Sponsored by InMobi) 上写真:JustCo GranTokyo South Towerにて撮影 SKANに基づく独自のターゲティング技術 ―自己紹介及び貴社の事業紹介をお願いします。 InMobiの広告事業部門とAIによるショッピング体験を提供する当社独自のエージェンティック型ショッピングプラットフォーム「Glance AI」の責任者を兼任するクナル・ナグパと申します。 当社はInMobi DSPやInMobi Exchangeを含む複数の広告プラットフォームを提供しています。InMobi ExchangeについてはThe Trade Desk、DV360、Amazon DSPなど主要なプラットフォームと接続することで既に世界中で利用されており、2026年以降は日本市場のバイサイド関係者との直接的な連携を強化していく予定です。 またB to Bとなる広告事業とは別に、B to C事業に該当するAIを活用したエージェンティック型ショッピングプラットフォームとなる「Glance AI」の運営も行っています。 東京オフィスには現在20名ほど在籍しており、モバイルアプリ向けのユーザー獲得やリターゲティング支援及び当社に出資するソフトバンク株式会社を始めとするパートナー企業様との連携促進などに注力しています。 ―DSP市場には既に多数のプレーヤーが存在します。貴社の強みは何でしょうか。 DSP市場自体は確かにコモディティ化していますが、iOSでの広告配信について深い専門性を持つ企業はAppleを除くとほぼいません。そして、このiOSこそがまさに当社の得意領域であり、LTVの高いiOSユーザーを対象としたターゲティング機能を提供しています。 AppleがSKAdNetworkをリリースした際に、業界は「フィンガープリントなどの回避策を見つける」と「SKAdNetwork(現AdAttributionKit)の枠組みの中で最大限の成果を出す」という二つの対照的な選択肢のいずれかを選ぶことを迫られました。そして当社は、ユーザーのプライバシーを保護するという大前提に立ち、あえて一般的には広告配信規模が限定されてしまう後者の道を選んだのです。そしてこうした制限下においても十分な広告配信規模を確保できるまでに技術を磨き上げました。 ―iOSを得意領域とするということは、広告在庫はアプリ配信面が主となるのでしょうか。 創業から18年の歴史を持つ当社は、そのうち17年間はアプリ広告配信をほぼ専業としてきました。アプリこそが消費者が最も時間を使う場所であると確信していたからです。社内外から配信面を多様化すべきという意見を耳にしても、私はアプリだけに集中すべきだと考えていました。 しかしながら、現代の広告主はデジタル配信において200社近くのパートナーと連携する必要があります。InMobiがアプリだけでなくウェブやCTVにも配信面を広げることで、広告主の負担の軽減に繋がると考えを改め、多様な配信面の統合に踏み出しました。また近年ではCTVの重要性も飛躍的に増しました。よって今ではウェブやCTVにも対応しています。 JustCo GranTokyo South Towerにて撮影 ―Glance AIと呼ばれる新規プラットフォームの概要を教えてください。 Glance AIは、消費者に高度に関連性のあるコンテンツやショッピングのインスピレーションを提供する、AIを活用した当社のエージェンティック型ショッピングプラットフォームです。 その中核にあるのは、ユーザーの意図を理解し、最適なコンテンツ体験をリアルタイムで提供するLLM(大規模言語モデル)ベースのシステムです。主な機能は2つあります。 まず一つが「未利用資産」の活用。現状では全くの「未利用資産」と化しているスマートフォンのホーム画面に関連性が高くパーソナライズされたコンテンツを提示します。日本ではシャープ社が製造するスマートフォンのロック画面にネイティブ統合しました。またアプリとしても提供しており、AndroidとiOSの双方で利用可能です。 さらに主要なTV事業者との提携を通じて同じく「未利用資産」と化しているCTVのスクリーンセーバーにも最適で、購買意欲を掻き立てるようなコンテンツを表示しています。 ー未利用かつ最も目を引く資産ということですね。 数十単位のアイコンの中から利用するアプリを選び出すという仕組みはそろそろ限界を迎えてきたと思います。当社としてはいずれGoogleやApple等もホーム画面を活用した同様のソリューションを大々的に展開してくるのではないかと想定しています。 もう一つの大きな特徴は、Eコマースプラットフォームとしての機能も持ち合わせているということです。例えば、今年大きな注目を集めたロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手のハイライト映像を見て、「ドジャースの公式ユニフォームを着てみたい」と思ったとしましょう。Glance AIは、ユーザーがそのユニフォームを着た姿を表示し、しかもワンタップで購入することができます。 従来であれば、MLB公式ストア訪問→ロサンゼルス・ドジャースのページを探す→商品を探す→サイズを選ぶ→カートに入れる→決済情報を入力するという手続きを必要としていたプロセスが、わずか数秒で完結します。 我々は過去20年にわたり「Googleの検索結果として数百万単位のリンクが表示される」という世界を生きてきましたが、今やChatGPTが登場したことで、リンクではなく、答えそのものが返ってくるようになりました。つまり自分の疑問を適切に伝えることさえできれば、その答えを得るのにスクロールやクリックはもはや不要です。Glance AIを通じて、Eコマースでも同様の世界を構築したいと考えています。 ―2つの主要な機能はどのように関係しているのですか。 Eコマース機能においても大規模言語モデルに基づき極めて関連性の高いコンテンツを表示することができます。例えば、「今日は火曜日」「東京は雨」「都心のオフィスを訪問予定」といった状況を踏まえて、「今日のあなたはこういう服装が最適です」という提案をしてくれると同時に他の候補もいくつか提示してくれます。そして気に入った提案をクリックすると、その服を着た自分の姿を合成した画像が表示され、サイズを自動判定してそのまま購入することが可能です。 Glance AIの表示画面例 つまり、サイズを調べる必要も、試着する必要もない。時間を1秒も無駄にしないこの買い物体験を一度でも経験したら、従来の購入プロセスには戻ることができなくなるでしょう。逆にマーケターにとっては、①購入率の大幅な上昇、②新たなオーディエンスの発掘、③とりわけZ世代の感覚にフィットするエンターテイメントの提供といった利点を得ることができます。 CTVをブランディングとダイレクトレスポンスの両方の目的において活用できることを私たちが実証したいと思います。 ―今後の事業展開をお聞かせください。 まずはGlance AIのユーザー数を世界で5億人規模にまで拡大したいと思います。 また2026年は、日本市場において当社の事業体制とプロダクトがすべて揃う年となると考えています。今回の日本出張においても、公共交通機関で移動するなどして、できる限り日本の消費者の行動をつぶさに観察することに努めました。 これまで日本市場では、主にDSP事業を軸に展開してきましたが、アドエクスチェンジ事業そしてGlance AIが揃ったことで、統合的かつ極めてユニークなマーケティングソリューションを今後は提供していく予定です。 InMobi Japan|note 採用情報|キャリア|InMobi InMobi日本語ニュースレターに登録
新世代のシゴト観―“媒体支援”から“自社の仕組みづくり”へ:朝日新聞社 小祝 結佳氏
異業種からデジタル広告業界へ、そして新聞社のデジタル事業部門へ――さまざまなフィールドで経験を重ねながら、データ活用の可能性を追い続けてきた人物がいる。朝日新聞社メディア事業本部 プランニング部データドリブンチームで、データを活用した広告商品の設計や運用に携わる、小祝 結佳氏だ。 朝日新聞グループ横断のデータ基盤を活かし、営業や企画部門と連携しながら、メディアの新しい価値づくりに取り組んでいる。 デジタル広告業界で培った経験をもとに、媒体側でデータ活用に取り組む。そこには、変化を前向きに捉え、社内外の関係者と協働しながら成果を積み重ねてきた実務家としての姿がある。本稿では、小祝氏のこれまでのキャリアを起点に、働くことや業界との関わり方についての視点を紹介する。 異業種から広告の世界へ──変化を恐れず踏み出したキャリア 大学卒業後、小祝氏はエネルギー関連商社に入社した。LPガスや産業ガスを扱う企業で、家庭用および業務用機器の仕入れや販促企画を担当していた。 「全くアドテクとは関係ない会社にいました」と振り返る。当時から「より新しい分野に挑戦したい」という思いがあり、3年間の勤務を経てIT業界への転職を決めた。 転職先では、ネイティブ広告ネットワークを手がける企業で媒体営業を担当。広告商品の導入支援や運用を通じて、デジタル広告の仕組みを実務として学んだ。 広告運用の成果を数値として確認できる点に、デジタル広告ならではの面白さを感じたという。 その後、女性向けメディアを運営する企業へ移り、広告収益化業務を担当。「媒体側の目線に立って携わりたいと思った」と話すように、広告配信の最適化や分析を通して、メディアの収益構造に深く関わる経験を積んだ。 前職では自社メディアの広告収益化を担当していたが、会員組織やファーストパーティデータのような基盤は保有していなかった。「ファーストパーティデータは持っていなかったので」と本人も語るように、データを活かした広告展開への関心が次第に強まっていった。 その後、ファーストパーティデータを持つ大規模媒体での取り組みに関心を持ち、朝日新聞社への転職を決意した。 メディアの収益を支えるデータ活用の取り組み 朝日新聞社入社後、小祝氏はメディア事業本部で、ファーストパーティデータの活用を軸とした広告プランニング業務を担当している。 その基盤となるのが、グループのデータプラットフォーム「A-TANK」だ。朝日ID会員の属性情報、行動データ、記事閲覧データ、オフラインイベントの参加情報などを統合し、広告設計や分析に活用している。 広告実施時のターゲティング設計から、実施後の効果測定・レポーティングまで、データをもとにした運用を担当している。 データを扱う業務には技術的な知識だけでなく、周囲との調整や理解を合わせる力が求められると小祝氏は語る。 新しい仕組みを社内外に浸透させるためには、丁寧な説明と信頼関係の構築が欠かせない。データ活用は単なるテクノロジーの話ではなく、組織や人とのつながりを前提とした取り組みでもある。 オープンな組織で育つ、挑戦を支える文化 朝日新聞社という伝統ある企業において、デジタル領域の職場はどのような環境なのか。 「入社する前は雰囲気がつかみにくかったのですが、実際に働いてみると、とてもフラットで意見交換がしやすい職場でした」と小祝氏は語る。 チームには若手メンバーも多く、議論や情報共有が活発だ。「ジャーナリズム精神がある会社なので、納得いくまで議論して進める文化があります。その点はデジタル領域でも変わりません」と話す。 大きな組織でありながら、部署をまたいだ協力体制が整っており、課題があればすぐに相談して動けるスピード感があるという。 こうしたオープンな職場環境が、新しい領域に挑むモチベーションを支えている。 コミュニケーションを軸にした仕事観 日々の業務では、社内外の多様な関係者と連携する場面が多い。 「ミーティングお化けになりつつあるんですけど」と笑う小祝氏だが、会議の多さはそれだけ関係者との調整が多いことの裏返しでもある。 「知識が先行してしまうと相手に伝わらないことがある。だからこそ、相手の立場に立って話すことを意識しています」と語る。 その姿勢を表す比喩として、「自分の魂を口から出して相手の体に入れて考える」という印象的な言葉も残した。 勤務形態は週3日の出社と週2日の在宅勤務を組み合わせるハイブリッド型。 「長時間働くよりも、メリハリをつけて働きたい」と話すように、効率的で柔軟な働き方を実践している。 キャリアを通じて描く、業界のこれから アドテク業界に関わってきた年月の中で、小祝氏が最も感じるのは「変化の速さ」だ。 「最近は明るいニュースばかりではないけれど、逆風が吹くなかでも新しいソリューションが次々と出てきている」と語る。 プライバシー規制や広告単価の変動など、業界が直面する課題は多いが、それを前向きに捉えて挑戦を続ける企業が多い点に希望を見いだしている。 また、業界の横のつながりの強さにも言及する。「競合同士でも情報交換をする空気があります。イベントや勉強会で自然に知見を共有する場面も多い」と話す。 今後のキャリアについては、「これまでとは異なる領域やフォーマットにも関心があります」と展望を述べる。データ、メディア、テクノロジーが交わる場所で、自身の経験を活かして新しい価値を生み出していきたいという。 地元・横浜で過ごす時間は、仕事の切り替えにもなり、日々のエネルギー源となっている。野毛の小さな店での会話や交流が、日常のリズムを整える大切な時間になっているという。 異業種からデジタル広告業界に飛び込み、複数の企業で経験を重ねた小祝氏。変化を前向きに受け止め、関わる人々と共に課題を解決していく姿勢が、彼女のキャリアを形づくっている。 データと人をつなぐその仕事観は、これからのメディア産業における新しい可能性を示している。
広告の未来を再定義する一日— ATS Tokyo 2025 総括
過去最多となる468名が一つの会場に集った「ATS Tokyo 2025」。 広告業界が直面するシグナルロス、AI、データコラボレーション、アテンション、リテールメディア、透明性、規制、そして広告文化の原点まで、1日を通じて多層的な議論が行われた。本稿では、全セッションの主要発言と示唆をもとに、ATS Tokyo 2025が提示した業界の潮流と課題を総括する。 シグナルロスとデータ主権:広告基盤の再構築が始まる オープニングでは、IAB Tech Lab Anthony Katsur 氏が、現在のデジタル広告を揺るがす4つの構造課題を提示した。同氏は「ブラウザやOSの制限により、広告シグナルは過去にない規模で失われている」と語り、AI・LLMの普及により「検索エンジンを経由した従来の送客モデルが崩れつつある」と警鐘を鳴らした。 その解決策として提示したのが、コンテンツ単位でアクセスと利用を管理する COMP(LLM Content Monetization Protocol) である。さらに、ライブイベント広告向けの LEAP、CTV透明性を向上させる OMSDK、そして広告処理をブラウザからサーバー側に移す Trusted Server Initiative を紹介し、「広告基盤を国際標準に合わせて再構築する時代に入った」と締めくくった。 続く「次世代エージェンシー論」では、Timers 栗城良規氏 が「代理店の専門性と速度は依然として重要だが、それを失えば外部依頼の意義は薄れる」と述べた。メルカリ 千葉久義氏 は「生成AIとインハウス運用の進展が代理店の役割を再定義する」と語り、両氏は「広告運用ではなく、事業構造に踏み込む伴走型支援こそ代理店の未来」である点で一致した。 OOHの再評価とパフォーマンス疲弊からの脱却 OOHセッションでは、ohpner 土井健氏 が「ターゲティングが効きすぎ、同じ池の魚ばかり取り合うラットレースが続いている」と指摘し、街中OOHがもつ“偶然の出会い”の価値を強調した。電通 櫻井順氏 は「OOHは公共空間に開かれているからこそ嫌われにくく、セレンディピティを生む点がデジタルにない価値だ」と述べ、加えて人流データや計測基盤の整備が進んだことで DOOHの計画・評価精度が高まりつつある と説明した。さらに櫻井氏は、「業界横断で 効果指標を整備する動きが進んでおり、OOHの測定環境が透明性の高いものへと近づきつつある」と語った。 パフォーマンスマーケティングのセッションでは、SUBARU 安室敦史氏 が「購買サイクルの長い自動車では、短期獲得だけでは市場形成は不可能」と述べ、心理的蓄積と行動指標を同時に追うKPI設計を紹介。電通デジタル 青木亮氏 は「獲得偏重から脱却し、上流接点を可視化することこそ代理店の価値」と語り、StackAdapt 山口武氏 は「ブランドと獲得の50:50が最も効率的」と説明した。 データコラボレーションとアテンション:広告指標の再定義 電通 前川駿氏 は「AIによる広告運用の自動最適化に依存しすぎると、計測できるユーザーの特性が偏ってしまう」と述べ、企業同士の1stパーティデータをデータクリーンルームでユーザープライバシーに配慮した環境で連携し、調査パネル・購買データ・キャリアデータを掛け合わせることで、より明確な顧客のインサイトを把握することができると強調した。 アテンション指標のセッションでは、KDDI [...]
UNICORN、メディア向け新サービス「UNICORN FOR:Publisher」を提供開始――収益性とユーザー体験の両立を支援
写真:ATSTokyo2024で登壇する山田 翔氏 UNICORNは、デジタルメディアの収益性向上とユーザーエクスペリエンスの改善を支援する新サービス「UNICORN FOR:Publisher」の提供を開始した。 本サービスは、広告を掲載する側であるパブリッシャーに焦点を当て、メディア運営の持続性向上と広告エコシステムの健全化を無償で支援するものである。 デジタル広告市場では、ページビューや広告枠数に依存する収益構造が一般化する一方、過剰な広告量や刺激的な表現の広告が増加し、ユーザー体験が低下する課題が指摘されている。この状況に対し広告主はブランドセーフティの観点から掲載面の選別を強めており、メディアは収益最大化とユーザー体験維持の両立というジレンマに直面している。 UNICORNはこうした市場構造の歪みに危機感を持ち、広告とコンテンツが調和したメディア空間の再構築に取り組む方針を示している。 UNICORNは、メディア空間の質が高まることでユーザー来訪が増加し、広告効果が向上し、結果として媒体の価値向上と収益安定につながると捉えている。「UNICORN FOR:Publisher」は、この好循環を実現することを目的に設計されている。 本サービスでは三つの支援機能を提供する。 第一に、メディアが保有する1st Party Dataを活用した広告配信を行い、そのデータ利用料をメディアに還元する。データはTreasure Data CDPに保管され、CDP利用料はUNICORNが負担するため、メディアは追加コストなしで新たな収益源を得ることができる。 第二に、Lumen Researchのアテンション計測ソリューションを用い、各広告枠における注目時間やアテンション率をメディアに提供する。これにより、ユーザーの注目を得にくい枠を特定・削減することで、全体の収益性を維持しつつユーザー体験を向上させる改善が可能となる。 第三に、メディアの特性や強みを踏まえた戦略立案や実行を通じ、ブランド広告主との接点拡大を支援する。 UNICORNは今後も「UNICORN FOR:Publisher」を通じて、ユーザー、広告主、メディアの三者が価値を享受できる広告エコシステムの実現を目指すとしている。併せてアドウェイズグループ全体として、国内外で実用的な広告マーケティングサービスの開発を進め、持続可能な市場環境の構築に取り組む方針である。 アテンション計測導入と媒体支援が一貫した課題意識のもとで展開 UNICORNによる「UNICORN FOR:Publisher」の開始は、同社が先に発表したLumen Researchとのアテンション計測導入と方向性が一致している。アテンション計測は、広告枠ごとの“見られ方”を可視化し、広告主・媒体双方の改善に活用するものである。 一方、今回の新サービスは、媒体がそのデータを活用し、枠改善や収益改善に取り組むための支援を直接提供するものであり、両施策は補完関係にある。 また、ATS Tokyo 2024での山田翔代表の登壇では、広告がユーザーに十分読まれていない状況や、媒体側がAttentionデータに基づき枠を理解する重要性が述べられていた。 今回の二つの発表は、この問題提起と整合した内容となっており、広告品質向上に向けた実行段階へ移行していることが確認できる。 これによりUNICORNは、広告主向けのアテンションデータ提供と、媒体向けの枠・収益改善支援の両面から、広告効果とメディア価値の向上に作用する施策を展開していることが明確となった。
自らデータ分析に取り組み、最適な施策を目指す-アイモバイル 芳賀 百菜氏
デジタル広告業界で働く広報・マーケティング担当者は、専門性が高く難解な業界用語と向き合いながら、形として見えにくい自社プロダクトやサービスを、日々顧客をはじめとする様々なステークホルダーに、ストーリー性をもって分かりやすく伝え、自社のブランド価値を高めていくことが求められる。 そんなミッションをもつ広報・マーケティング担当者は日々何を考え、どんなことに向き合っているのだろうか。デジタル広告業界の広報・マーケティングのプロフェッショナルにインタビューを行い、彼らのリアルに迫る。第7回は、株式会社アイモバイルの芳賀 百菜氏にお話を伺った。 (聞き手:ExchangeWire JAPAN 角田 知香) 【インタビュー対象者】 芳賀 百菜氏 株式会社アイモバイル メディアソリューション事業本部 東京営業部 メディアコンサルタントグループ 新卒で通信サービス事業会社に入社し、UI/UX及びコンバージョン率の改善やBtoC向けのマーケティング・開発ディレクションを担当。外資系ヘルスケアカンパニーに転職、市場データや顧客動向の分析、ブランド全体のマーケティング・販売戦略を担当した後、「データ分析を駆使したマーケティングがしたい」という思いのもと株式会社アイモバイルに入社。オウンドメディア運営やイベント企画に加え、事業データの分析を通じてマーケティング施策の立案や改善を担当している。 【インタビュー対象企業】 株式会社アイモバイル 「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに、インターネット広告とコンシューマ事業を展開する。広告事業では、国内有数の規模を誇るアドネットワークを中心に、複数の広告プロダクトも活用したパブリッシャーの収益最大化を行うメディアソリューション事業やアフィリエイトやインフルエンサーマーケティングなど多様な広告ソリューションを提供。コンシューマ事業では、ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」をはじめ、地域体験型サービスを通じて地方創生に貢献している。広告と消費者サービスの両軸で、マーケティングを起点とした新たな価値創造を推進する。 -現在ご担当されている業務領域を教えてください。 メディアソリューション事業本部でマーケティングおよび広報業務を担当しています。自社オウンドメディアの企画・運営、セミナーなどのイベント企画運営や、ホワイトペーパー・プレスリリースの作成なども行います。 弊社にはプロダクトを作るチームと営業チームがありますが、私はこの2つのチームの橋渡しをする役割だと考えています。作ったプロダクトをどう売っていくかを整理し、データを起点としてマーケティング戦略を立てます。広報とマーケティングを兼任しつつ、自ら事業データを分析し、市場動向や顧客行動を可視化することで、よりデータに基づいた施策を目指しています。 -主な顧客層をお聞かせください。 私が所属するメディアソリューション事業本部では、ウェブサイトやアプリを運営するパブリッシャーの方々を主な顧客として、広告収益の最大化を支援しています。Google認定パートナーおよびSSP事業者として、広告配信の最適化や収益構造の改善など、各パブリッシャーの課題に合わせたソリューションを提供しています。 相談内容に応じて、最適な人に力を借りる -会社全体の雰囲気はいかがですか。 会社が掲げる行動指針である「Smile × Growth × Team」のValuesの通り、社員が主体的に、かつ協力して切磋琢磨できる風土があると感じます。いい意味で遠慮せず、自分の意見を述べることができて、きちんとすり合わせができる環境です。 業務の中で不安や疑問がでたときは早めに誰かにアドバイスを求めるようにしています。「データ分析のことはあの部署のあの人に聞いてみよう」というように、内容に合わせて最適な相談相手を考えます。部署で広報とマーケティングを兼任しているのは私一人ですが、案件内容に応じて社内の専門メンバーに相談できる体制が整っているため、安心して業務に取り組めています。 -どのような業務に時間を割くことが多いですか。 事業データの分析や施策の効果検証に最も時間を割いています。アイモバイルに入社するとき、「SQL(構造化照会言語)を使ってデータ分析ができる」ということが大きな魅力でした。SQLやBIツールを使って取引実績やトレンドを可視化し、その分析結果に基づいてマーケティング施策を調整していきます。 自らデータ分析をすることで説得力をつける -積極的にデータ分析に取り組むモチベーションは何ですか。 アイモバイル入社1年が経ったころに実際SQLを使えるようになり、そこからどんどんこの分野を極めたいと思うようになりました。 これまで数社にわたってマーケティングを担当してきました。フロントに立ってくれる営業部隊に「こういう風に進めてほしい」と要望を伝える際に、しっかりデータという根拠を持って方針や戦略を伝えたいということは、常に心にありました。やってほしいことを伝えるからには、自分自身で手を動かしてデータ分析をすることで、ミーティングなどでも自信をもって意見や物事を伝えることができると考えています。 データを積み上げたあとは、伝える相手によってどういう伝え方がベストか、ということを意識しています。できるだけ全体像を先に伝えて、データをもとにしながら、代案もセットで話し、相手の温度や言葉を意識しながら進めていきます。 -業務で注力していることは何ですか。 マーケティングという幅広い業務の中で大切にしているのは「データ」です。自分でSQLを使ってデータを分析し、現状の把握や課題の仮説を立てる、そこから「何を作ればいいのか」「どうやって売ればいいのか」をチームで議論して施策に繋げていきます。データを見るだけでは売上にはつながらないので、「データをアクションに繋げる」という役割をいつも念頭に置いています。 社内のデータアナリストと協力しながら、数値の変化だけを分析するだけではなく、背景にある要因を整理することで、どのアプローチが最も効果的かということを検討するプロセスを大切にしています。データ起点で議論を深めることで、チームでの意思決定の精度を高められるよう意識しています。 -いま最もPRしたいことを教えてください。 SNSやAIが中心となる時代だからこそ、オープンインターネットの価値を改めて見直す必要があると考えています。 メディアソリューション事業本部では、Webやアプリを運営するパブリッシャーの皆さまが保有するコンテンツ価値を最大限に活かし、収益成長と運営効率の両立を支援しています。 Google認定パートナーとして培った知見をもとに、広告配信の最適化や運用サポートを行い、オープンな広告環境で成果を出せる仕組みづくりに取り組んでいます。
- Latest news
ニュースレター(WireSync)に登録
ExchangeWire Japanの最新情報を毎週まとめてお届けします

![iOS上のターゲティングと未来型コマースで差別化-InMobi独自の戦略とは[インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/12/top1-280x187.jpg)




![オープンインターネット市場に巨大プラットフォームが出現―新生Teadsが掲げる「Elevated Outcomes」とは [インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/09/teads-top.jpg)


![[Global動向]イギリスにおけるデジタル広告費、二桁成長の見通しほか](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/09/0925global.jpg)

![「デジタル広告業界の課題はそう簡単には尽きない」―「広告主等向けガイダンス」を発表した総務省に聞く[インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/09/MIC-top-to-be-published.jpg)
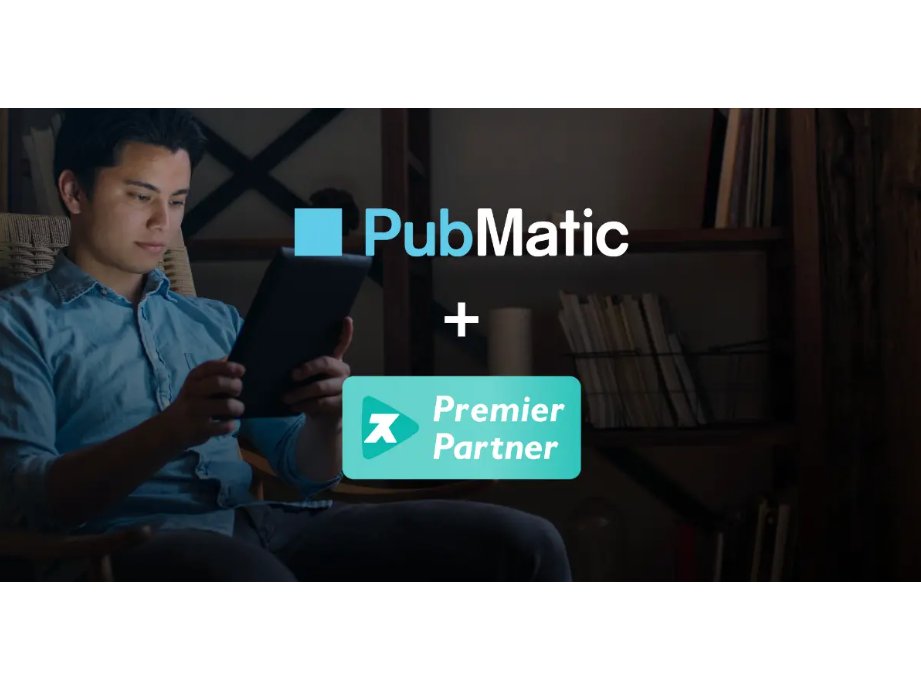
![[Global動向]トランプ大統領、TikTokと合意に達するほか](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/09/0919global.jpg)


